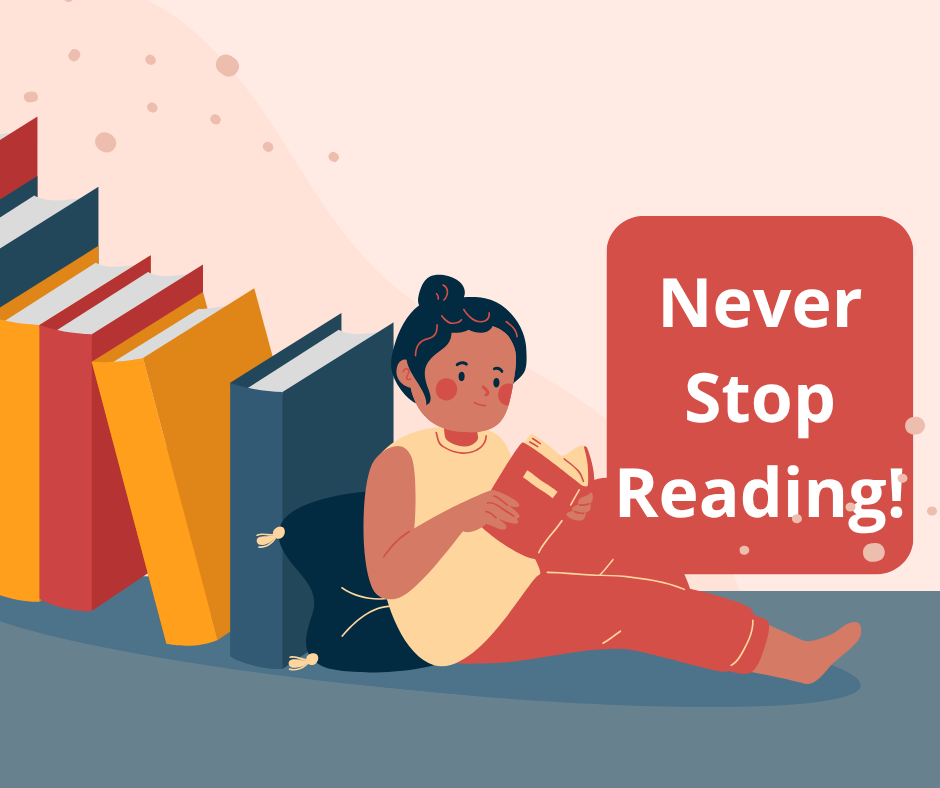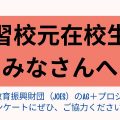読み聞かせ、やっていなくても大丈夫?
子育て中、「絵本の読み聞かせ」はどのぐらい大事なのか?というのはよく話題になることです。
やった方がいいだろうな、となんとなく思っている人も多いのではないでしょうか。
まじめなお母さんは 1日何冊読まないといけないのか? といった質問への「正解」を求めて
ネット検索することもあるかもしれません。
アメリカでは約四分の一、つまり25%ぐらいの子供が幼少期に本を読んでもらっていないという統計があったり、
オーストラリアではその割合が5分の3、つまり半数以上だとか、
イギリスでは読み聞かせてもらっている子供が特に男の子で減少していて、読書嫌いが増えている、
などなど、読み聞かせの重要性を訴える調査研究は数多く発表されています。
日本では2004年に文科省が発表したアンケート調査結果があります。
これによると割と多くの子供が「よく読んでもらった」「時々読んでもらった」と回答しています。
読み聞かせをした頻度については、半数以上が毎日か1日おきに読んでもらっています。
また、読み聞かせをしていた時期は5、6歳までが多いですが、小学校低学年・中学年まで読んでもらった子供も25%以上います。
最近はどうなっているのか、気になります。


5歳までに「100万語」の差が出るという見解について
最近のいろいろな国のデータをみていると、読み聞かせをする家庭が世界的に減ってきているのかな
という印象があります。
読み聞かせの調査が行われているのは、読み聞かせが 子供の読む力 や 認知力
などの学力だけでなく、共感力 なども育てるために重要だという研究が
これまでに数多く発表されているからです。
そんな研究の一つに、5歳までに読み聞かせをよくしてもらった子供と、
してもらわなかった子供の間に、聞いたことのある言葉の数にどのぐらい差が出るか
を考察したものがあります。
研究者たちはまだ文字が読めない幼児向けの、典型的な読み聞かせに適しているといわれる本を選んで、
どのような絵本をどのような時期に読むかなどの要素も考えた上でその語彙数を計算。
5歳まで毎日5冊ぐらい読み聞かせをしてもらった子供は、5歳までに140万語以上を聞いている
のに対し、ほとんど読んでもらっていない子供は4000語程度であると結論付けています。
ちなみに 週に1~2回だと 6万3000語、週に3~5回で 17万語、毎日1冊だと 30万語
という計算です。
日常生活で幼児期に、どのぐらいの語彙を聞いているのかどうかを調査することは
なかなか困難であることは予想されますが、
アメリカで1992年に発表された研究で、
裕福で識字率の高い家庭の子供と、貧困層の子供では3歳までに語彙数にして
3000万語の差が出るとしたものがあります。
このような調査や、読み聞かせをしない家庭が25%もあるということから、
読み聞かせの多寡によって聞く語彙に
どのぐらいの差が出るかを計算した研究が行われたのだと思われます。
実際に子供はそれだけの言葉を聞いたからと言って、それをそのまま使うようになることは
もちろんないわけですが、読み聞かせが語彙数や認知力に影響があるというほかの調査結果もある
ので、親は「読み聞かせをすべき」という考え方があるわけです。
ただ、もちろん読み聞かせればいいというものでもないですし、
親も読み聞かせだけやってるわけにはいきません。
それに、バイリンガルの場合はその数がどんなに頑張っても両方の言語で
半分になってしまう! と心配する人もいるかと思います。
読み聞かせをあまりしていなくても、とても良い子に育った、バイリンガルもうまくいった、という例もきっとあるでしょう。
なんといっても、言語や子供の発達する環境というのは、変動する要因が本当に多くありますから。
バイリンガルの子供の語彙数が、モノリンガルの子供に比べて少ないということはよく言われますが、
両言語の語彙数を計算するとそこまで差はないという研究結果もあります。
幼児期には、親がその時一番安心して子供に話しかけることができる、得意な言語で、お話をしたり、
読み聞かせをしたりするのが一番、大事です。
(それが親の母語であることも、そうでないこともあるでしょう。)
バイリンガルの子供についてですが、いずれにしてもその子にとって
軸となる言語がしっかり発達していきさえすれば、心配することはあまりないのです。
バイリンガル子育てについては、以下の記事なども書いています。
「目標」に向かって進むということ
このようなトピックでいつも思うのは、「目標」に向けて がんばる、努力する という考え方が
子育てや教育には本来、しっくりこないんじゃないかなあ、ということです。
子育てや教育は目標があって、そこに向けて工程を効率化することなど本来できない。
目の前の子供や教育の課題にただ、向き合い、そこから何ができるか、そこで何が楽しいか、
そこで何が一番有意義と思えるかということを、
毎日、その時を大事にただひたすら、長い長い一日を、それでも年月で考えたらあっという間の時間を
どう過ごすか、その時その場で一番良いと思える答えを親子で、あるいは教員と子供で考えて出していくこと
なのではないかと思います。
もちろん、目標を持つことは大事です。
それを否定はしません。
ただ、そこに到達することだけを考えるというのは
間違った方向に行ってしまわないよう
よく気を付ける必要がある
というのが私の教育・子育て感です。
ちょっと話がそれましたが、それでも楽しく読み聞かせをしたり、幼子と話したりすることについては
自分なりにがんばってはいましたが、
もっと大事にしてもよかったんじゃないかなあ…
と思うこともあります。
そもそも、現在に至るまで、日本で楽しそうにする子育てって、あんまり
模範例が多くはないんじゃないでしょうか。
こういう時、海外のママさんたちを見るとなるほどな~と思うことが、私はあります。
子供とのやりとり、こんな風にいっつもできてたら、楽しそうだな~
自分は3人目で少しだけできたかもしれないな~
という感じで鑑賞しながらフォローしている人たちがいますので、今度、整理してみます。