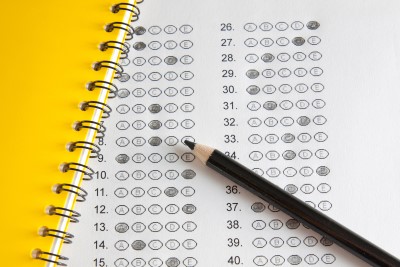目次
ハーバード大学、アジア系志願者への差別で訴えられる
2月といえば日本では大学受験シーズンたけなわ。でも米国の高校生は大体、出願がひと段落してほっと一息ついている時期です。
米で、いや世界的に有名な大学といえば、私立名門といわれるアイビーリーグ8校。
特にハーバード大学はその筆頭として有名です。
ちなみに、カリフォルニア州の名門私立大学スタンフォード大学も日本でも有名ですが、こちらはアイビーリーグではありません。
アイビーはあくまでも東部の歴史のふるーい、名門校のことを指します。
2018年、そのハーバード大学の入学基準をめぐり、アジア系応募者に対してだけハードルが高く設定されており、人種差別だとしてあるアジア系団体が訴訟を起こしました。

裁判になると当然原告、被告の双方から様々な文書が提出・公開されます。
米国名門私立大学の入学基準は、日本のように入試結果重視ではなく、課外活動や社会的貢献度をみることは知られていましたが、大学側からはそれらの明確な合格基準が示されることはあまりありませんでした。
ですからこの裁判で大学側から出された資料は注目を集めています。
日本でもこの裁判については報道されていますが、ハーバード大学側が公表した入学基準の詳細などはあまり紹介されていないようです。
大学側の文書からは、合格を判断する基準は6項目で、ポイント制だが「全体的」に審査されること、そして学業と課外活動以外には、スポーツと人間性が重視されていることがわかりました。
以下で大学側の文書からわかる、入学基準の詳細を見てみます。
ハーバード大学の合格判断基準6項目
ハーバード大学の説明によると、入学志願者は「ポイント制」で評価されます。
判断の基準とされるのは6項目。
学力はその1項目に過ぎません。
全6項目はこちら↓です。
- 学業(Academic)
- 課外活動(Extracurricular)
- スポーツ(Athletic)
- 人格(Personal)
- 推薦状(2通は教員から、1通はカウンセラーから)
- 志願者とインタビューを行った卒業生の個人的・全体的評価
各項目の評価の仕方ですが、非常に優れていれば1、優れていれば2、という風に6段階の評価がつけられます。
米国などでの学校の成績はA+, A, A-などのようにプラスやマイナスがついたりしますが、それと同じように1+, 1,…などと、6段階からさらに細分化されることもあるようです。
特徴的なのは、ポイント制といえど、各項目の点数を足していって合計し、上位を入学させる、というわけではないということです。
評価は「全体的(holistic)」に行うそうです。
だから6項目すべてで1の評価がもらえれば、合格はほぼ確実。 などといった簡単なものではなく、全体の項目を見て、全体的にその志願者が1から6の評価のどこに入るかを決定するようです。
米国の名門大学は、学力だけではなく課外活動をしなければいけないから大変、という認識はすでに持っている人も多いかと思いますが、それどころではなく、スポーツをがんばり、人間性も磨かないと入学の確率は高まらないということです。
(スポーツが苦手でも、入学した人はもちろんいます。)
そして全体の評価として1がつけば、合格はほぼ確実。
2だと合格の確率は65%。
これが3になると、いきなり9%に下がります。
これは全体の合格率とほぼ同じとなります。
アジア系の志願者は、成績が良く、課外活動で全国レベルの大会で一位や二位をとってもアイビーリーグに入れないのは差別だと主張しているのですが、スポーツや人格、その他全体、さらには多様性も考慮していると主張する大学が差別を行っていると判断することはなかなか難しいように思えます。
成績と課外活動は重要だが、人間性やその他のプラスアルファで差がつく?
ちなみに、2018年の入学を目指し、ハーバード大学に出願したのは4万2749人。
合格したのは1962人で、合格率は5%を割り込む4.59%でした。
このうち、成績がオールA(完璧)だった志願者は8000人。
統一テストのACTで満点得点者(英語・数学両教科)は625人、同じくSATは361人。
SATの数学の満点得点者は3500人。英語(verbal)の満点は2700人だったそうです。
これをみればわかるように、このような志願者の中では、成績では差はつかないのです。
当然ですが統一テストでは、日本の東大入試のような難問は出ません。
ほぼ全員、満点かそれに近い成績です。それも何度も受験したわけではなく、平均受験回数は2回です。
つまり基礎学力をみています。
満点が無理でも、全体をみて選考するので、チャンスはあります。
どれだけ困難な状況を克服したか。
どれだけ自分が情熱を持っていることを追求したか。
世の中にどれだけ貢献したいと思っているか。
そういうことが重視されます。
高校生としてはかなり成熟している子どもたちが求められているわけです。
例えば、出願時に提出する文章の1つに、「#BlackLivesMatter」と100回繰り返しタイプしてスタンフォード大学から合格通知をもらい、話題になった若者がいます。
でも当然ですがそれだけで合格したわけではありません。
成績が良かったのはもちろん、何よりも自分で非営利団体を立ち上げて運営し、2016年の大統領選ではヒラリー・クリントン陣営でボランティアもしています。16歳でTEDxYouthのトークも行っています。
卒業生のインタビューからわかること
またあるアイビー大学の卒業生は、高校生のインタビューで「世界中の人(死んだ人も含め)誰とでも話ができるとしたら誰と何を話したいか?」という質問をしたときの回答例で、ポイント1をもらえる人とそうでない人の差を示していました。
ある生徒は、有名ミュージシャンの名前を何人か挙げ、その理由はただ「その人の曲が好きだから」と説明。特に印象に残らない回答例といえます。
一方ある生徒は歴史上の人物や哲学者の名前を挙げ、その理由を詳細に述べ、インタビューする彼もそれらの人物に非常に知的な興味を掻き立てられたといいます。
この場合、どちらの生徒が高評価を受けたかは明白です。
これ以外にも、インタビュアーが感心するような高校生はまだまだいるようです。
ホームレスが絵を描いてストレスを緩和させることができるよう、プロジェクトを考えて、周りの反対も押し切りそれを成功させる、とか。高校生が、です。親が一部手伝ったとしても、インタビュアーにはおそらくその情熱が本物かどうかはある程度判断できるでしょう。推薦状やその他エッセーなどでそれが裏付けられるかどうかなどは確認されると思いますが。
とにかく米国名門大学入学は狭き門です。
でも、何が求められているのか、ということは、大学側のポイント制の詳細と、卒業生のインタビュアーの話などから、わかってくるのではないかと思います。
もちろんこれ以外にも様々な要素が考慮されることもありますが、それについてはまた次の機会に触れることにします。