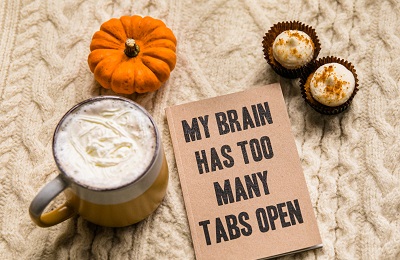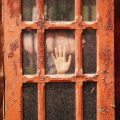バイリンガル(の脳)への偏見
バイリンガル子育てにがんばっているのに、バイリンガルに対する否定的な意見を見たり、聞いたりするとへこむこと、ありますよね。
上の「バイリンガルの脳の特徴」シリーズ記事でも、バイリンガルに対する偏見が長く続いていた時期があることに触れられていましたが
バイリンガルだと要するに「脳の半分」の容量だけしか使えない というような
とんでもない考え方が今でもみられます。
こちらで紹介しましたが、現在のバイリンガル教育の基礎を築いた ジム・カミンズ(Jim Cummins)氏が提唱してきたように
しっかりとした基盤が1つの言語で育っていれば、それは別の言語の基礎にもなる
ということは、数十年にわたって いくつもの研究データで裏付けられてきています。
アメリカ・カナダでもバイリンガルは少数派
ただ、多くの国や地域では、2言語といっても
その言語同士の力関係が同じではないので
どちらかというと社会的に優勢な、多数派の言語、
例えばアメリカだったら 英語 が
義務教育のキンダー(日本では年長)辺りから強くなり
マイノリティ言語の日本語を使い続ける動機が
親にも、子どもにも維持しづらくなることがあります。
両言語で言葉がとても流暢だったり、学習水準が学齢レベルに達しているというバイリンガルは
確かにそれほど多くはないかもしれません。
国をあげて全面的にバイリンガルを支持しているところも
そう多くはないですし、
そういう国であるカナダでさえ
公用語である英仏のバイリンガルが全人口に占める割合は
20%以下。
意外と少ない、と思われる人の方が多いのではないでしょうか。
(もちろん、地域によってかなり異なります)
ちなみにアメリカでも、過去10年ほどの間にバイリンガルの人口は2倍に増加しましたが
やはり、全人口に占める割合は20%程度です。
(家庭言語と英語のバイリンガルを数えているため、割合的としてはカナダと同程度になっているのではと思われます)
バイリンガルの先輩・ロールモデル
周りにバイリンガルのロールモデル、「頼れる先輩」がいない人は多いと思います。
でもそんな偏見には負けず、自分の道を力強く切り拓いているバイリンガルの先輩たちはちゃんといます。
そのような先輩は、もちろん努力家の人が多いですが、
「モノリンガル」、つまり英語だけできればよい、という見方が強い北米で
それに対抗できるような環境や機会に恵まれたということもあるのではないかと思います。
また、そこまで「バリバリ」(?)でなくても
普通に、日常的に2つの言語を使い分け、自分の道をしっかり歩んでいるバイリンガルも大勢います。
親が子どもときちんと話をしながら ともに歩んでいく子育てができるのであれば
バイリンガルでもそうでなくても
あまり関係ないのではないかは思います。
また、簡単そうなことではありますが、そのような子育てが
バイリンガルでもそうでなくても
実はなかなか難しいのではないでしょうか。
いずれにしても、バイリンガルに対する偏見がかなり根強いと
以前から感じていますので、当サイトでも折に触れて バイリンガルの「先輩」たちの話を掲載してきましたが
ここにデービス出身のトリリンガルの「先輩」の記事を紹介したいと思います。
彼は、ポート・オブ・サクラメント補習授業校の卒業生でもあります。
創立30周年の記念式典のときに披露してくれた歌声はとても素敵でした。
※後からこの時の記念冊子を見て思い出したのですが、この時の伴奏は
FaaB・バイリンガル子育ての会でお話を聞かせてくれたゆりかさんでした!
バイリンガルには、いろいろなタイプがあります。
2言語がほぼ同等に、学齢水準で成人以降までいくケースもあれば、
途中から日本語、あるいは英語が主要言語になるケースもあります。
でも決して バイリンガル=セミリンガル(ダブルリミテッド)ではありません。
もし仮にそうであれば この卒業生のようなマルチリンガルは
一度に脳の容量の3分の1しか使えないことになりますが
そんなわけはないことは明らかです。
バイリンガルは普段、脳の半分しか使っていないことになる というような見方は
かなり短絡的で偏見に基づいた見解です。
このような偏見に疑問を呈し、研究を積み重ねてきたのが
私も一学生としてお世話になったジム・カミンズ(Jim Cummins)博士で
その研究の知見は ここ数十年にわたって覆されていません。